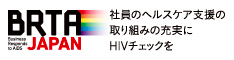“物言う経営者”マーク・ベニオフ率いるセールスフォース・ドットコムに見る
社会貢献をキャッチフレーズだけに終わらせない実効的システムの作り方
顧客情報管理サービスをクラウドで提供するセールスフォース・ドットコムは創業者であるマーク・ベニオフ氏が様々な社会問題について積極的に発言することでも知られる。そもそもの企業理念が、ビジネスで社会を変えることだという同社。LGBTQイシューをはじめとする社会問題への取り組みについて、インダストリーバリューセリング事業本部、ビジネスバリューサービス、プリンシパル・コンサルタントのピーター・シマさんに聞いた。 (聞き手/宇田川しい)

株式会社セールスフォース・ドットコム
インダストリーバリューセリング事業本部ビジネスバリューサービス
プリンシパル・コンサルタント ピーター・シマさん
社会貢献活動を実効的にする「1-1-1モデル」
――セールスフォース・ドットコムはLGBTQイシューについてもそうですが、様々な社会問題について取り組んでらっしゃいますね。
ピーター・シマさん 当社の創業者であり会長兼CEOのマーク・ベニオフは「ビジネスは社会を変える最良のプラットフォームだ」と語っています。つまり企業は社会をより良くしていくものと言うのが、創業当初からの彼の考えなんです。それは、我々が提供するサービスが社会に役立つものであるべきであり、企業とその従業員は、そのビジネスから得たものを社会に還元すべきという考えなんです。そして、それをコンセプトとしてだけでなく、会社の制度もそれを実現するためにデザインされています。
――具体的にはどのようなシステムでしょうか?
シマ セールスフォースには「1-1-1(ワンワンワン)モデル」と呼ばれるものがあります。簡単に言うと製品の1%、株式の1%、就業時間の1%を社会に還元するというモデルなんです。製品の1%というのは、当社のサービスの1%相当分を無料や割引のライセンスでNPOやコミュニティなどに提供することで、株式の1%というのは要するに株価の1%相当額ということですが、これを社会還元のために使う。寄付の形であったり、NPOやコニュニティの活動をスポンサーする様なことです。最後に、就業時間の1%というのは従業員の年間就業時間の1%にあたる56時間を社会活動のために使って良いと決められています。なにをするというのは会社からは決められていません。従業員が自分で決めます。また、それは就業時間中でもいいですし、週末でもよく、教育のNPOへの講師としてのお手伝いや近所にあるコミュニティ活動への参加などに当てている人もいます。
――お金だけでなく、サービスも人もというところに本気度を感じます。
シマ そうですね。アメリカで創業したのが1999年、日本法人が出来たのが2000年。当初は1%といっても微々たるものでしたでしょう。しかし、大事なのは、創業当初から根本の考え方として社会への還元という考え方があり、成長を続けていながらも、しっかりとした形にしているということですね。
――アメリカでは、マーク・ベニオフ氏は社会に対して物を言う経営者の代表のようなイメージがありますね。
シマ 本人はそうは思っていないでしょう(笑)。元々、会社として社会問題に関わっていくと言う方針ではあったものの、その方針を社外にも有名にしたきっかけは、マークのツイッターでの発信でした。アメリカで反LGBTQな州法の制定が持ち上がったときにそれを批判するツイートをしたんです。「こんな法律が通ったらうちはその州ではビジネスができない」みたいなことをツイートしたんですね。これが大きな反響を得て、他の経営者も追随した。確かにアメリカでは経営者が社会課題に対して物を言うカルチャーはありますが、著書にある様に、本人も反響にびっくりしたそうです。ただ、その様な州法が制定されてはいけない、その州で働く従業員を守らないといけない、という理由が根底にありましたし、従業員と幹部の応援もあり、また、他の企業も賛同の声を上げたため、その州法は成立しませんでした。日本を含む米国外では、社会の変わり方が違うので、同じやり方ではうまくいかないことはわかっています。例えば結婚の平等についても「日本では結婚の平等が無いので、そこではビジネスできない」みたいなツイートはしません(笑)。日本の場合は、団体や企業同士が連携し、結婚の平等の権利がいかに大事なことかの声を一緒に上げていく努力をしています。例えば、Marriage For All Japanなどの団体や活動する個人と共に動きながら、アライを増やし、他の企業にも賛同をお願いする、などの活動です。
社内がセーフスペースであることの重要性
――そうした活動をして行くときに、先ほど出た1-1-1の仕組みは非常に役立ちますね。特に就業時間の1%を誰もが自由に社会貢献に当てられるというのは大きいのではないでしょうか。
シマ 最近は、従業員リソースグループなどの仕組みを採用する企業が日本でも増えてきました。しかし、まだまだ活動の主体が人事や総務、あるいは、広報によるものが多いという印象です。また、従業員が行動の主体となる従業員リソースグループがあったとしても、業務に使う端末などの機器は業務用のもので私的なメールをしてはいけないというような制約があったりして、就業時間外の個人の時間や個人の機器を利用して活動しているところもあります。従業員リソースグループを作るまではしたけれど、まだ会社全体の制度が追いついていない状況の一例です。セールスフォースの場合は、社会に還元する活動は、会社が認めていることですので、会社の資源を使うことが認められています。むしろ社会還元活動は推奨されています。従業員は、自分が選んだNPOやコミュニティに対して56時間以上のボランティア時間を申請すると「ボランティア・ロックスター」と呼ばれて顕彰されるんです。
――なるほど、日本の他企業と比べるとレベルが違いますね。
シマ 日本のOutforceの設立は4年前の2017年でしたが、アメリカ本社では、ずっと前から従業員リソースグループの仕組みはありましたので、立ち上げてからのサポート体制は出来ていました。活動の仕方のロールモデルが会社の中に多数いたというのは大きいです。日本の企業も、このような活動を始めているので、情報交換をして日本に合った活動が増えるよう、応援しています。
――そうした環境の中でシマさんはLGBTQグループの一員として活動されてるんですね。
シマ はい、私はその従業員リソースグループの中で、LGBTQ+の当事者が直面する課題に取り組み、啓蒙活動などを経て、みんなが平等に扱われ、自分らしさを表現できる空間、つまり、セーフスペースとなるよう活動するグループOutforceでリーダーをしています。その活動の中で最も大きいのが、東京レインボープライドのスポンサーになり、プライドウィークに合わせた活動なのですが、マーケティングを含む会社を上げてサポートしてくれています。スポンサー予算も、事業部から頂きました。でも、活動の主体はOutforceにあります。
当社にも「アライってなに?」というような人もいます。事業が拡大するにつれて、色々なバックグラウンドを持って、他企業から入ってくる人も増え、こうした企業カルチャーに初めて触れるという人も増えました。ですから、常に学びの場を設けることも必要で、また、色々な視点を通して学ぶために、外部講師を呼んだセッションを設けたりもしています。そして、こうした活動に力を入れてきたおかげで、新入社員の中には「LGBTQイシューに積極的に取り組んでいるからセールスフォース・ドットコムで働きたい」と言って入社した当時者もいます。現在、新型コロナの影響で、イベントはリモート開催になっていますが、それでも200名以上が参加しています。
――先ほどおっしゃっていた1-1-1の仕組みで自由に活動出来るというのも大きいですね。
シマ 自由に活動出来るという意味では、社内が様々なコミュニケーションの中で差別や批判が入ってこないスペースであるということは重要だと思います。企業によっては、ガバナンスの観点から全てのメールのやり取りをモニタリングしているところもあります。それが、直属の上司によって行われていたりします。すると、社内が自由にコミュニケーションできる「セーフスペース」でないと、センシティブな内容の議論ができません。
例えば婚姻の平等実現への課題は、法律論、憲法論でもありますが、深いところで感情論でもあると思います。つまり「どうして同性同士だと結婚できないの?」といった率直な思いから「同性同士の結婚は嫌だ」などの感情の問題でもあるんだと思うんです。そうした率直な思いについて自由に話し合うためにはセーフスペースであることが必要です。これは社会貢献についてだけでなく、創造性を大切にする企業であれば、従業員が自由に動けるスペースを作ることは重要ではないでしょうか。そして、従業員が自由に動けるということは、会社として従業員を信用しているというメッセージです。だから従業員も信頼に足る人間であろうとする。当社はコアの部分で信頼で成り立っているんです。
LGBTQの問題はSOGIの問題であり女性問題ともつながっている
――セールスフォース・ドットコムではLGBTQの問題に限らず広く平等を目指していますね。
シマ はい。セールスフォースにはイクオリティオフィスと言うのがありまして、広く平等を目指すプログラムがあります。その中でLGBTQ+の課題にフォーカスしているのがOutforceなんです。なので、セールスフォース全体としてはブラックライブズマターや、最近のアジア人とパッシフィックアイランダーへの暴力問題にも対応している従業員リソースグループもあります。というか、暴力を伴う差別に対しては、特定グループとか関係ないですね。そして、アジア人がなかなか外資系企業のトップに立てない、ガラスの天井ならぬ「竹の天井(バンブー・シーリング)」という問題にも取り組んでいます。ところで、知ってますか?アメリカでの直近の政権交代によってこうした活動がずいぶんやりやすくなったことを。以前、アメリカでマイクロ・アグレッションに関する取り組みをしようとしたところトランプ政権から横槍が入って中断を余儀なくされていたそうです。イクオリティのオフィサーのトップからそんな裏話が政権が変わった今になって出てきたりしています。こういう話はなかなか日本には伝わってこなかったんですが、グローバルでプログラムが動かなかったわけですから、トランプ政権の影響というのは日本でも小さくなかったんですね。
――先ほど日本では女性問題への取り組みが立ち遅れているとおっしゃいましたが。
シマ ジェンダーギャップですね。ここにはジェンダー・ステレオタイプの問題があると思います。男女ともに「男はこうあるべき」とか「女性はこういう服装をするべき」とかの考えに無意識に縛られている。私はLGBTQということをテーマに活動していますが、これをSOGI(ソジ、性的指向・性自認)の問題として捉え、性自認はバイナリー(どちらか一つ)ではないと思っているので、このステレオタイプすることがジェンダーギャップの問題にも繋がっていて、結局はSOGIへのイクオリティでありエクイティの問題に帰ってくると思うんです。

外資系だから出来るのではない、なければ自分で作ればいい
――こうした取り組みは外資系だから出来るけど、日本の企業では難しいと言う人もいます。
シマ でも、私は前に日系の企業にいて、こうした取り組みが何もないところから「えい!作っちゃえ!」って1から作ったんですよ。それまで外資系にいて、LGBTQグループなどが仕組みとしてなくてもネットワークを作るというのが当たり前のカルチャーの中にいましたから、動いちゃいました。まず、人事に「草の根的に活動しますね」と宣言して、LGBTQのイベントに行ってはイベントリポートを出して、としばらく続けていたら、「うちの会社としてもこういう活動をしなきゃいけない」という考えの人が人事に来て、一緒にやりましょう!というふうになって行きました。
――それは、これから活動を始めたいと思っている人はとても勇気づけられる話だと思います。そういう人に何かアドバイスはありますか。
シマ まずは直属の上司の理解ですね。あと、上司に限らず、とにかく敵を作らない。協力してくれなくても、妨害しないだけでいいんです。その人の価値観が自分と違うのは、その人の育った環境や経験で決まってきます。そこに良い悪いはない。その結果として知らないということを責めるのではなく、どうしたら知ってもらえるかを考えた方がいい。だから人事の人が知らないと言ったら、「こんなイベントがありました」という報告を続けたんです。「他にもこんな企業がきてましたよ」と。
――「どこの会社もみんなやってます」というのが日本の企業にはいちばん効くかも知れませんね(笑)。
シマ そうですね(笑)。「どこどこの会社は部長まで来てました」みたいに報告すると、「あぁ、周りはみんな動いてるのか」と理解してもらえました。あるいは、ライバル心燃やして、「うちもやるぞ!」という効果もあったりします。
――TRPはそういう意味でも役に立ちましたか。
シマ もちろん役に立ってます。LGBTQのネットワークを立ち上げようとしていた当時、TRPで元の同僚に会って勇気づけて貰ったり、他社でLGBTQの問題に取り組んでいる人たちと相談したりなど、共通の課題に取り組んでいる人たちとTRPで顔を合わせて繋がりを確認しあったり、また愚痴も言い合ったり出来て、同じ気持ちの人がこんなにいるんだ、孤独じゃないんだと思うことで、活動を続けることが出来たんです。それも、室外のイベントなので、室内で話すより良い方向に話が向かいやすいですし。そして、アライの方達を連れていくと、LGBTQの課題が他人事ではなく、自分事に変わるイベントでもあるので、とても役に立ってます。




























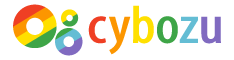















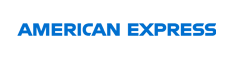













.png)